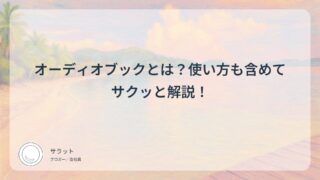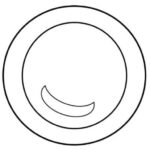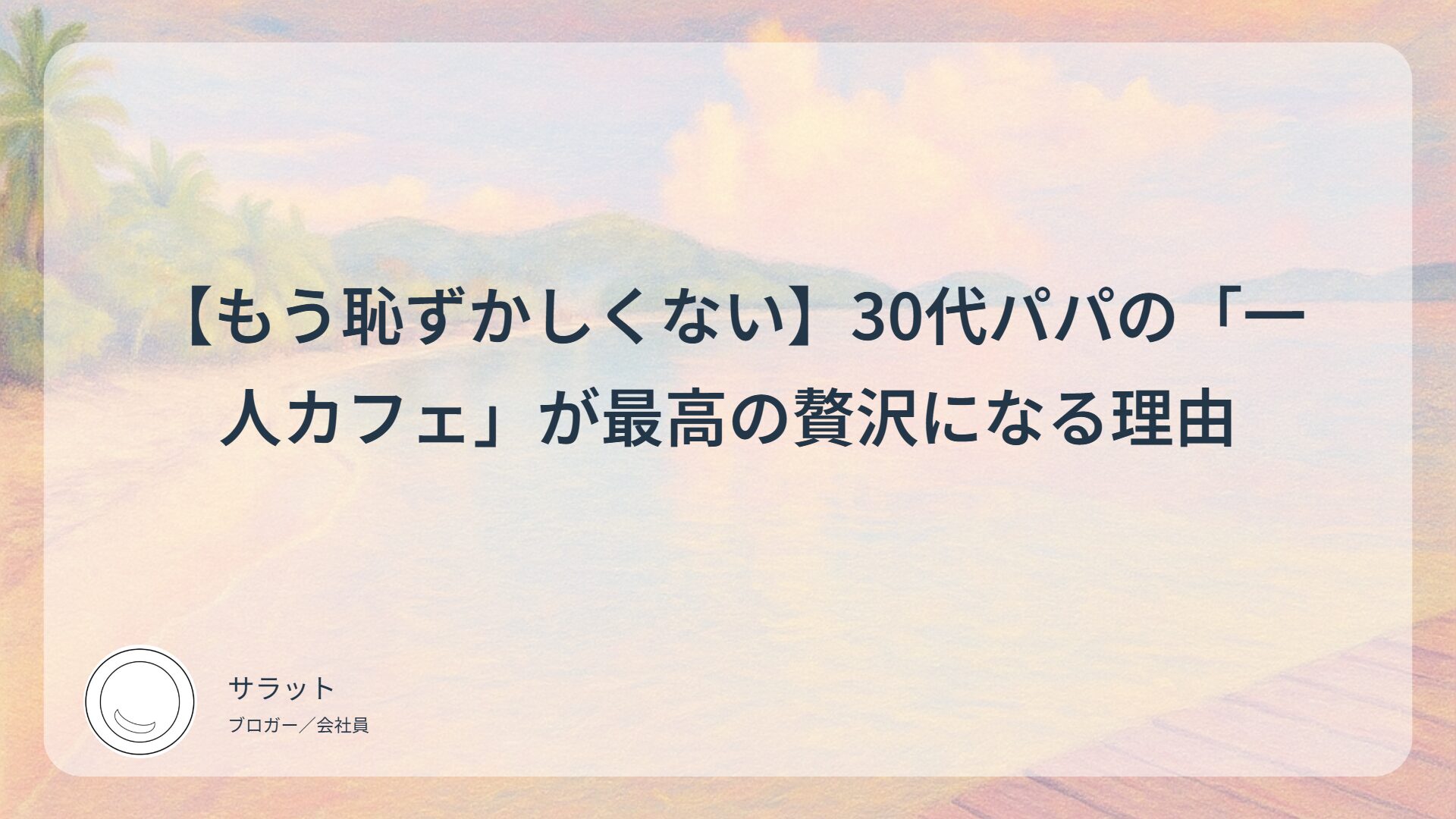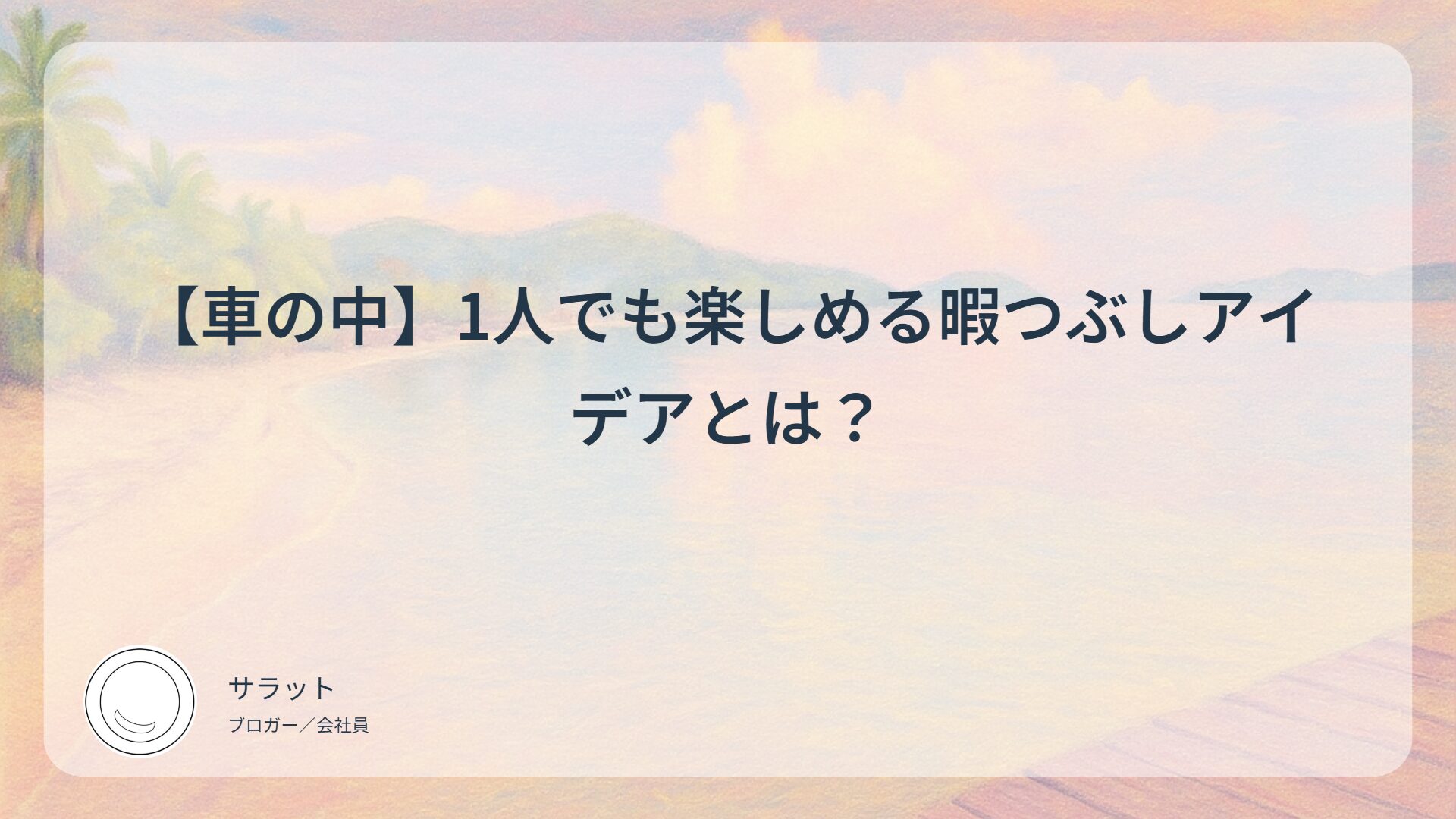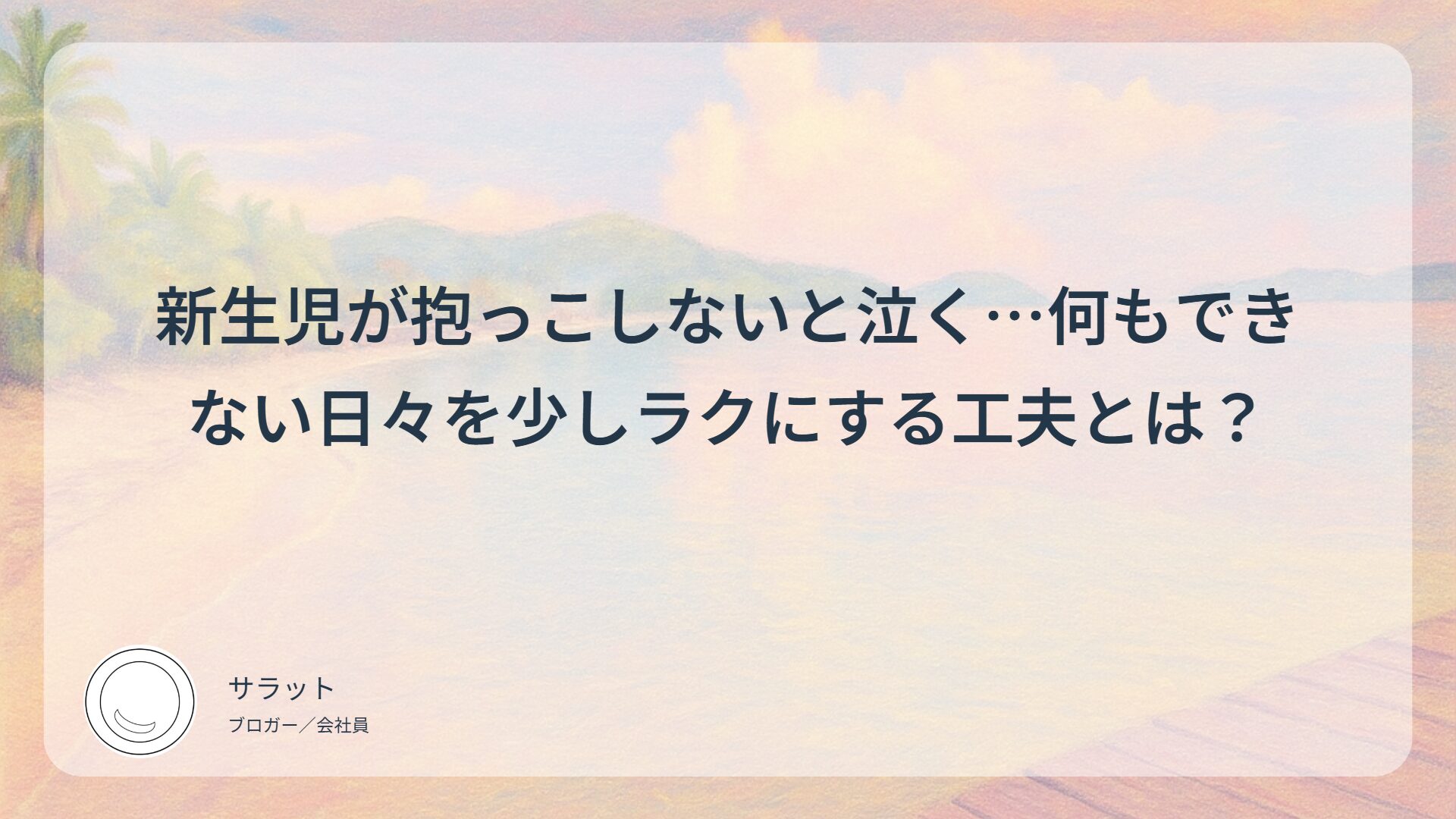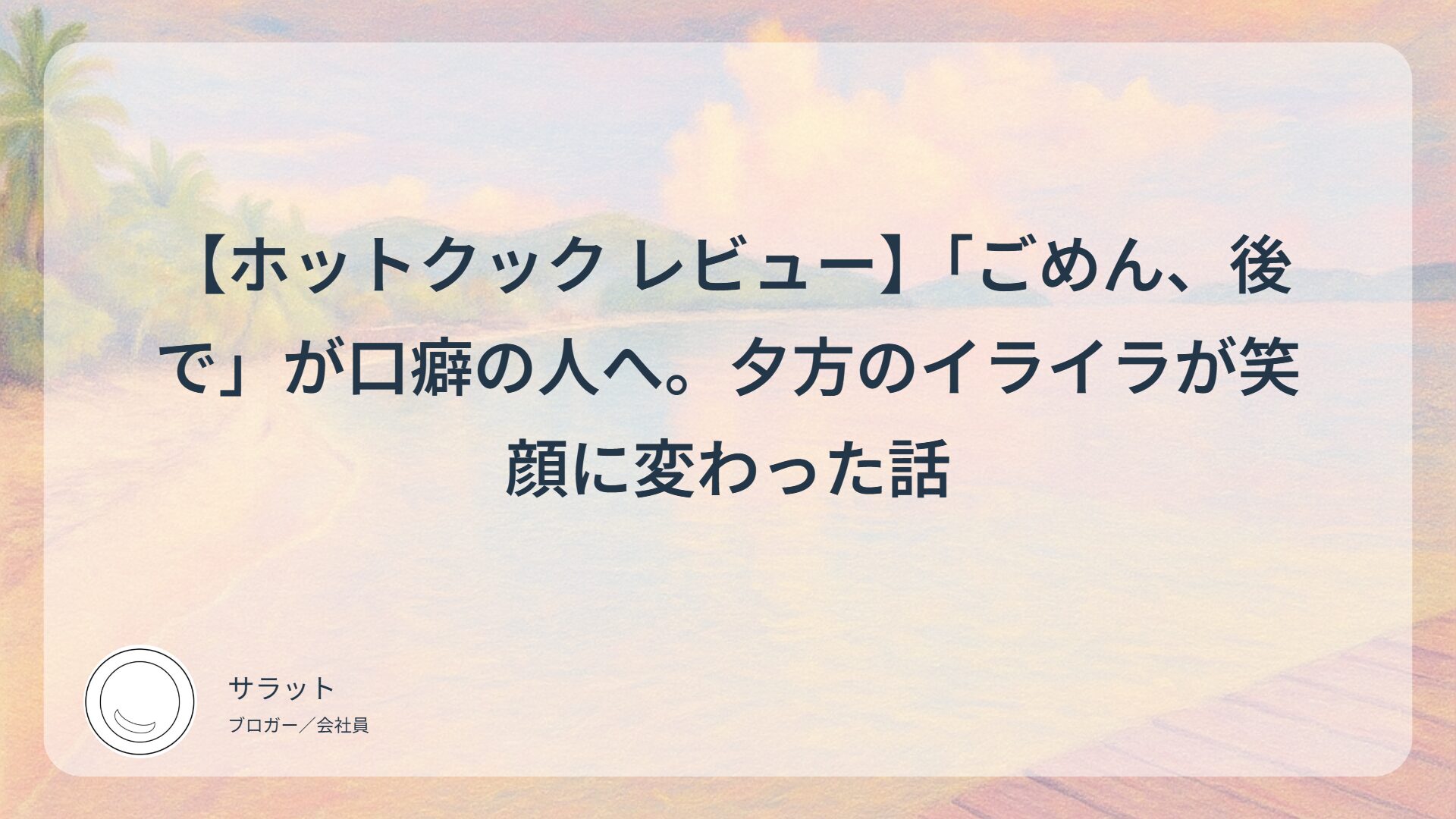寝る前、スマホ以外に何をする?我慢しなくても自然に手放せる夜の工夫
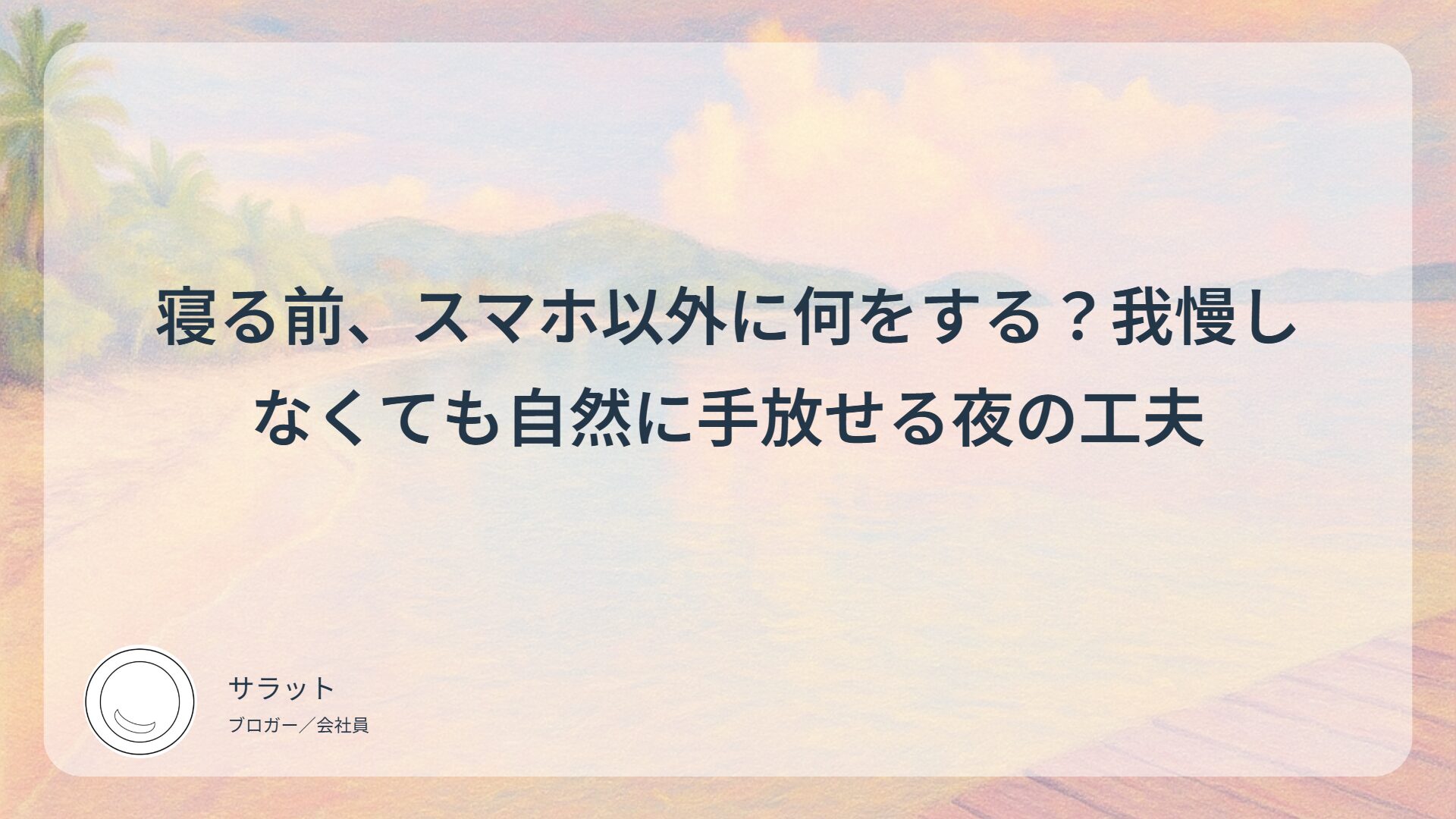
寝る前はついスマホを触ってしまう…
布団に入ってもスマホを眺めて、気づけば30分、1時間…
目も頭も疲れているのに、なぜかスマホをやめられない…
スマホを持つのが当たり前になった昨今、上記の悩みは決して珍しくないですよね。
特に、忙しくて自分の時間がないと感じる人ほど、寝る前のスマホ画面にどっぷり浸かっているのではないでしょうか。

寝る前って他人から邪魔されにくい時間帯。使いたくなる気持ち、わかります。
一方で、寝る前のスマホってあんまりよくないのでは?と感じ、やめたいと思う人がいるのもまた事実。
この記事では、無理に我慢することなく、自然とスマホから離れられる“夜の過ごし方”をご紹介します。

意識を変えるより、行動を変えるほうがラクなのです。
「コレ、いいかも!」と思えることがあれば、ぜひ取り入れてみてください。
この記事をかいた人(サラット)
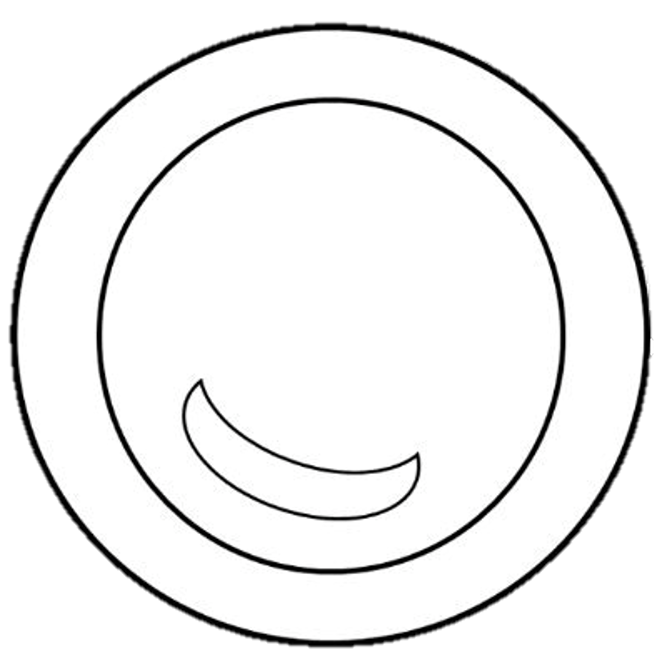
- 都内在住の二児(長男3歳・次男0歳)の父
- 教育業界にて会社員歴12年目
- 育休を2回取得(1回目:1か月、2回目:6か月)
- 営業職→企画職へ転職&フルリモート勤務を実現
- 年間の読書量は50冊以上
- 詳しいプロフィールは”コチラ”
寝る前のスマホ、実はかなり損してるかも?
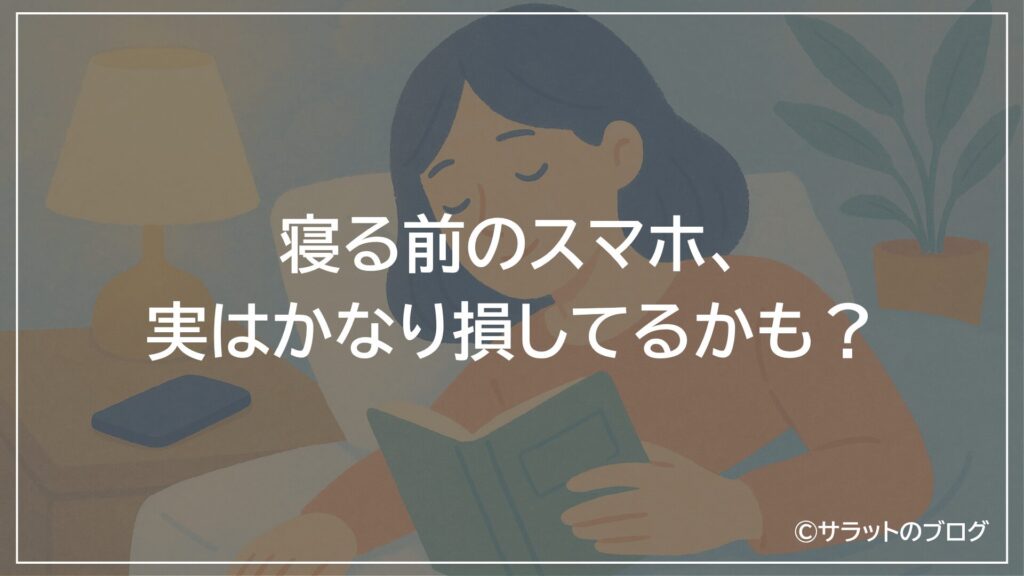
寝る直前までスマホを触ってしまう…
多くの人がそう感じつつも、なかなかやめられないのが現実です。

しかし、寝る前のスマホには思っている以上に悪影響があります…
ここでは、なぜ寝る前のスマホ習慣が“損”なのか、3つの理由でわかりやすく解説します。
これを知ることで、自然とスマホを手放したくなるかもしれません。
ブルーライトが脳を“夜モード”にしてくれない
スマホのブルーライトは、脳の睡眠準備を妨げてしまいます。
ブルーライトは朝日と似た光の性質を持ち、脳を覚醒状態に保つ働きがあります。
そのため、寝る直前までスマホを見ると、脳が「今はまだ起きている時間」と誤認し、自然な眠気がこなくなります。
これはちょうど、真夜中にカフェインたっぷりのコーヒーを飲むようなもの。
心地よく眠るはずの時間に、体を“活動モード”に切り替えてしまうのです。

せめて画面のダークモードはONにしましょう(私もやっています)。
「ちょっとだけ」が、いつの間にか30分経過…
寝る前のスマホは、時間を無意識に奪われやすい行動です。
スマホ操作はスクロールひとつで次々と刺激を受けられるため、時間感覚が麻痺しやすくなります。

「ちょっとSNS見てから…」のつもりが、いつの間にか30分!なんてザラですよね…
これは、ポテトチップスを「一枚だけ」と手を伸ばしたのに、気づいたら袋が空になっているのと同じ。
スマホも、やめどきを見失いやすい“クセになる仕組み”があるのです。
翌朝のだるさは、実はスマホのせいかも?
寝る直前のスマホ習慣は、翌朝の疲労感や集中力低下を招きます。
スマホの光や情報による刺激で、入眠が遅れたり、深い眠りに入るまでの時間が伸びたりするため、睡眠の質が下がってしまいます。
これでは、たとえ睡眠時間が足りていても「なんとなく疲れが残る」という感覚に。
たとえば、布団に入っても近くで工事の音がしていたら、眠れていても熟睡感は得られませんよね。
スマホの光や情報も、無意識に脳を刺激し続ける“ノイズ”として働くのです。

スマホを寝室に置かないという選択もアリだと思います。
「やめる」ではなく「夢中になれる」夜習慣が重要
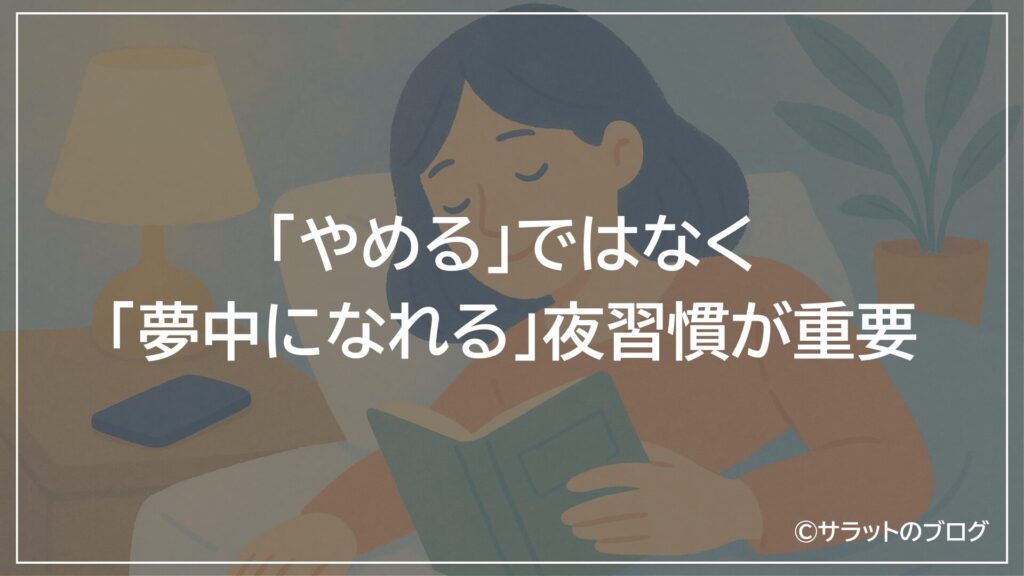
「スマホをやめなきゃ」と思えば思うほど、余計に触りたくなってしまう…

あなたにもそんな経験、ありませんか?
無理に我慢するよりも、自然とスマホを忘れられる“夢中になれる習慣”を探すことが、夜時間の過ごし方を変えるカギになります。
この章では、なぜ「やめる」より「夢中になる」が効果的なのか、その理由と考え方をご紹介します。
「やめよう」と意識すると、逆に意識してしまう
スマホを「やめよう」と意識するほど、かえってスマホの存在が気になるもの。
人間の脳は「◯◯しない」という否定命令に対して、それ自体を強くイメージしてしまう性質があります。
そのため、「スマホを見ない」と決めると、脳は“スマホ”を常に意識し続けてしまい、かえって誘惑に弱くなるのです。

「赤いゾウを思い浮かべないでね!」と言われると、つい頭に赤のゾウが浮かびますよね。
スマホも同じで、「やめよう」と思うほど意識が集中してしまうのです。
「代わりにやること」があれば、スマホが気にならなくなる
スマホをやめるには、“やめる”ことよりも“別のことに集中する”ほうが効果的。
人は何かに没頭しているとき、他の刺激への関心が薄れます。
特に感覚を使う行動(聴く・書く・動く)は、意識を一つに集中させやすく、スマホを触る時間を自然に忘れさせます。
たとえば、料理をしているときや好きな映画を観ているとき、スマホを手に取ることを忘れますよね。
同じように、何かに夢中になっていれば“やめようとしなくてもやめられる”のです。

スマホの通知も切っておくと更に効果的でしょう。
続けられるかどうかは、「義務感のなさ」がカギ
習慣にするには、「やらなきゃ」ではなく「やってもいい」という軽さが大切。
最初から意識高く構えすぎると、気が進まない日や疲れている日に「今日は無理」となりやすく、継続が途切れてしまいます。
反対に、心地よくできること・少しだけでもできることは、日々の負担になりにくく長続きするでしょう。
たとえば、毎日30分の運動を義務にすると挫折しがちですが、「ストレッチだけでもOK」にすると自然と続きますよね。

夜の習慣も、“小さな心地よさ”から始めるのがコツです。
寝る前のスマホ代わり!手軽で心地いい5つのこと
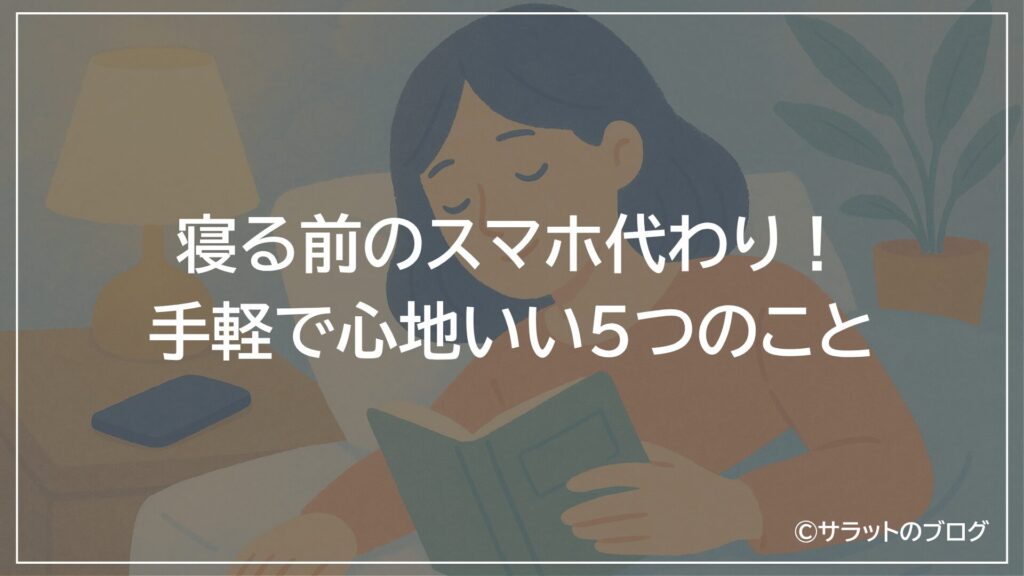
「スマホをやめよう」と思っても、ただ手持ち無沙汰になるだけでは結局また手に取ってしまうもの。
大事なのは、“スマホ以上に心地よい何か”がそばにあること。
ここでは、寝る前にすぐできて、リラックス効果も高く、自然とスマホから意識が離れる「5つのおすすめ習慣」をご紹介します。
オーディオブックで“耳だけ読書”を楽しむ
目を使わずに物語を楽しめるオーディオブックは、スマホ習慣の代わりにピッタリ!
視覚を休めながら聴覚を使って物語に没頭できるため、脳がリラックスし、入眠を妨げにくいのが特徴です。

スマホ画面の刺激も少なく、タイマー設定のお陰で寝落ちしても問題ありません。
たとえば、夜にラジオを聴いていると自然とまぶたが重くなる感覚がありますよね。
オーディオブックはその現代版とも言える存在。物語に浸ることでスマホを忘れて眠りに落ちやすくなります。
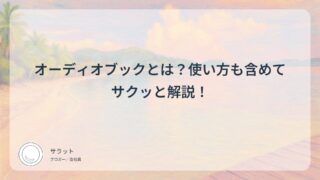
5分だけ“ゆるストレッチ”で体をととのえる
軽いストレッチは、体と心の緊張を解きほぐし、リラックスした状態で眠りに入りやすくなります。
日中の緊張やこわばりをほぐすことで副交感神経が優位になり、自然と眠気が訪れやすくなります。
深い呼吸を意識することで、気持ちの切り替えにも効果的!
まるで、ぴんと張ったゴムをゆっくり緩めるように、身体を軽く伸ばしてあげるだけで心もゆるんでいくでしょう。

お風呂上りとか、とくにオススメです。
ホットアイマスクや湯たんぽで、じんわり温める
目元やお腹を温めると、全身がゆるみ、眠りやすくなります。
温かさは自律神経を安定させ、自然な眠気を引き出してくれます。
とくに目元やお腹などを温めると安心感が高まり、体が“休息モード”へ。
冬のこたつに入ると、ほっとしてウトウトしてしまう感覚に近いです。

目元を温めるという意味で「ホットアイマスク」を使うのもよいかもしれません。
“今日の出来事”を3つだけメモする
軽く1日を振り返ることで、頭の中が整理され、気持ちよく眠りにつけます。
書き出す行為は思考を外に出すことにつながり、無意識に抱えていた不安や考えごとをリセットする効果があります。

書くのが習慣になると、1日を“閉じる”儀式としても機能するかも。
机の上を片付けてから仕事を終えるように、頭の中の“今日”を整えてから眠ることで、次の日に持ち越す雑念が減っていきます。
心地よい音楽をかけて、照明の中で“何もしない”を楽しむ
優しい音楽と落ち着いた照明の中で、あえて“何もしない”時間をつくることで、心と体が自然とリラックスしていきます。
音や光などの刺激を抑えた環境に身を置くと、自律神経が静まり、体は自然と「休むモード」へ。
忙しい毎日のなかで、“何かをしないといけない”というプレッシャーから解放される時間が、深い癒しにつながります。
これは、にぎやかな街を抜けて、静かな図書館に入った瞬間、ふっと力が抜けるような感覚に近いです。

余計な情報を敢えて遠ざけることで、心にスペースをつくるという発想です。
よくある質問とその回答
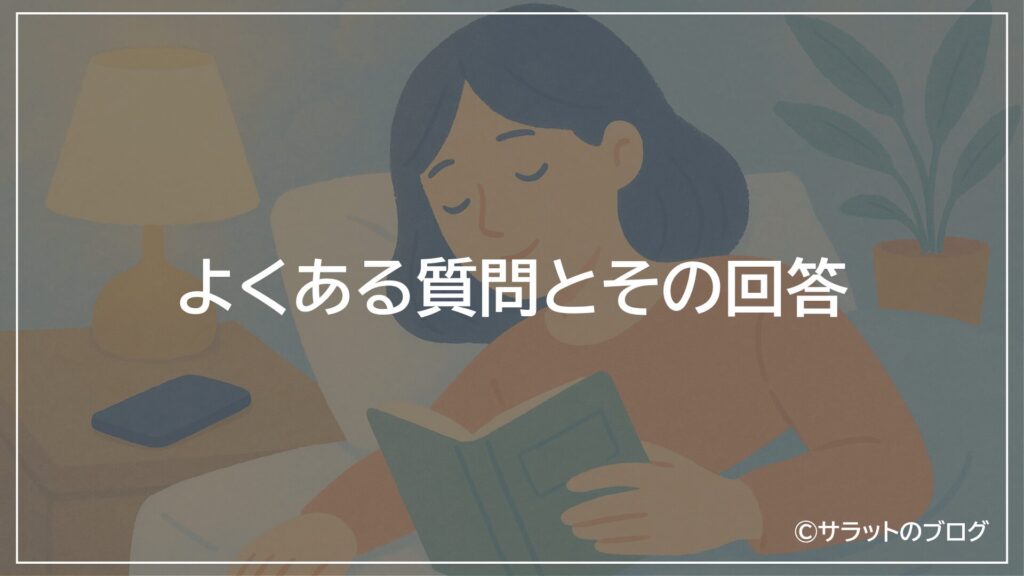
ここでは「寝る前についスマホを触ってしまって悩む」という人の、よくある質問に答えていきます。
- Q1:スマホ以外の習慣に変えようとしても三日坊主になってしまいます。どうしたら続きますか?
-
最初から「完璧にやろう」と思わず、1日5分だけでもOKとゆるく始めるのがコツです。気持ちいいと感じることだけを選び、「気が向いたらやる」くらいの感覚で取り入れると自然と続きやすくなります。
- Q2:スマホを見るのが習慣になっていて、気づくと触ってしまいます。どうすれば防げますか?
-
事前にスマホを別の部屋に置いたり、物理的に手元から離しておくことで、つい触るのを防ぎやすくなります。特に“代わりにやること”を決めておくと意識がそちらに向きやすくなります。
- Q3:寝る前に何かを始めると、逆に目が冴えてしまいませんか?
-
刺激の強いことや頭を使う作業は避けるのがポイントです。心と体をゆるめることを目的に、照明を落として、静かな環境でできる習慣を選べば、むしろスムーズな入眠につながります。
- Q4:寝室が明るいと寝つきが悪いと聞いたのですが、本当ですか?
-
はい、光の刺激は脳を覚醒状態にしやすいため、なるべく照明は暗めか間接照明に切り替えるのが効果的です。特にLED照明の白い光より、温かみのある色味のほうがリラックスしやすくなります。
- Q5:夜の習慣を変えたいのに、子どもの寝かしつけで自分の時間がありません。どうすれば?
-
すべてを完璧にやろうとせず、子どもが寝た後の5分を「自分のための時間」として意識するだけでも変化が生まれます。無理なく、無音でもできる行動から取り入れるのがおすすめです。
- Q6:寝つきが悪くて、何をしても眠れない夜はどうしたらいいですか?
-
「眠らなきゃ」と焦るほど眠れなくなるため、いったん眠ることを目的にしない“ゆるい過ごし方”に切り替えるのが効果的です。深呼吸や耳だけで楽しむ音声コンテンツが、脳の緊張をほぐしてくれます。
- Q7:夜にスマホを見ないと、情報収集や連絡が遅れてしまいませんか?
-
情報や連絡は“必要な時間帯に集中して見る”ことで十分に対応可能です。むしろ夜にスマホを断つことで、翌朝の集中力が高まり、トータルの情報処理効率が上がるケースも多くあります。
- Q8:本を読むのが苦手なので、読書習慣が定着しません。どうしたら?
-
無理に活字を読まなくても、「耳で聴く」スタイルや、漫画・イラスト解説つきの書籍なども立派な読書です。苦手意識を手放し、自分が楽しめる形式から始めてみてください。
- Q9:夜にリラックスできても、朝がつらくて結局元に戻ってしまいます。
-
夜の過ごし方が改善すると、徐々に睡眠の質が上がり、朝の目覚めもラクになっていきます。焦らず、まずは「昨日より少し気分よく眠れたかどうか」に注目すると習慣化しやすくなります。
- Q10:習慣化するために、何か道具を買うべきですか?
-
必ずしも道具は必要ありませんが、アロマ、照明、ストレッチマットなど、気持ちが上がるアイテムがあると“やりたくなる空間”づくりに役立ちます。気軽なもので十分なので、負担にならない範囲で整えてみてください。
まとめ:スマホを自然にやめられる夜の工夫を
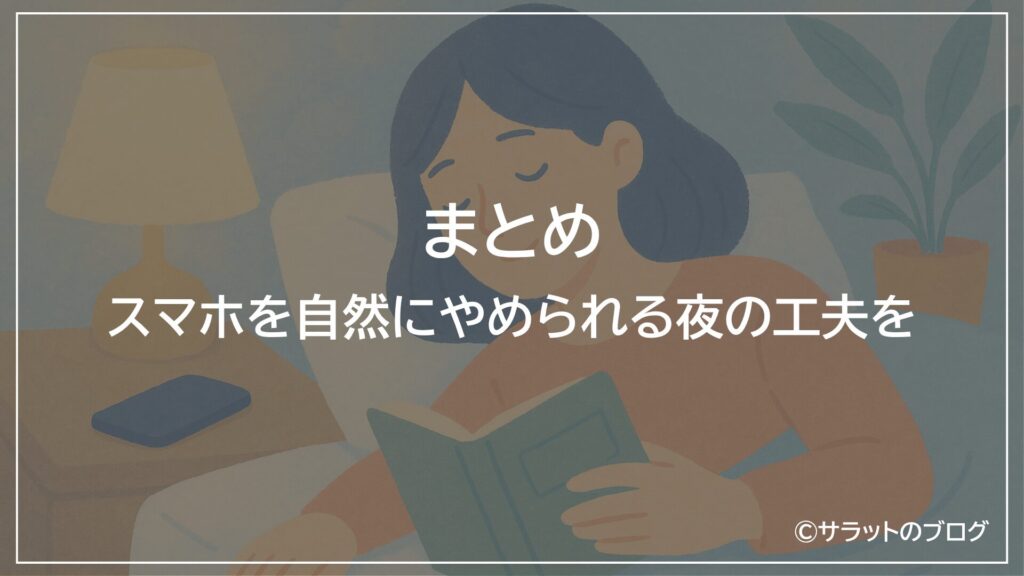
寝る前のスマホ習慣は、多くの人にとって「よくない」とわかっていても、なかなか手放せないもの。
でも、我慢したり気合いでやめようとしなくても大丈夫!
大切なのは、「スマホ以外に心地よい選択肢がある」ということを知り、自分に合ったものを取り入れていくこと。
オーディオブックでも、ストレッチでも、メモ書きでも、音楽でも、ほんの少しの工夫で夜の時間は大きく変わります。

あくまで、スマホを遠ざけるのは、心と体をいたわる一つの手段にすぎません。
やめることを目的にせず、「自然とスマホが気にならなくなる」夜の過ごし方を、今日から少しずつ試してみましょう!