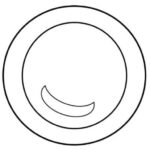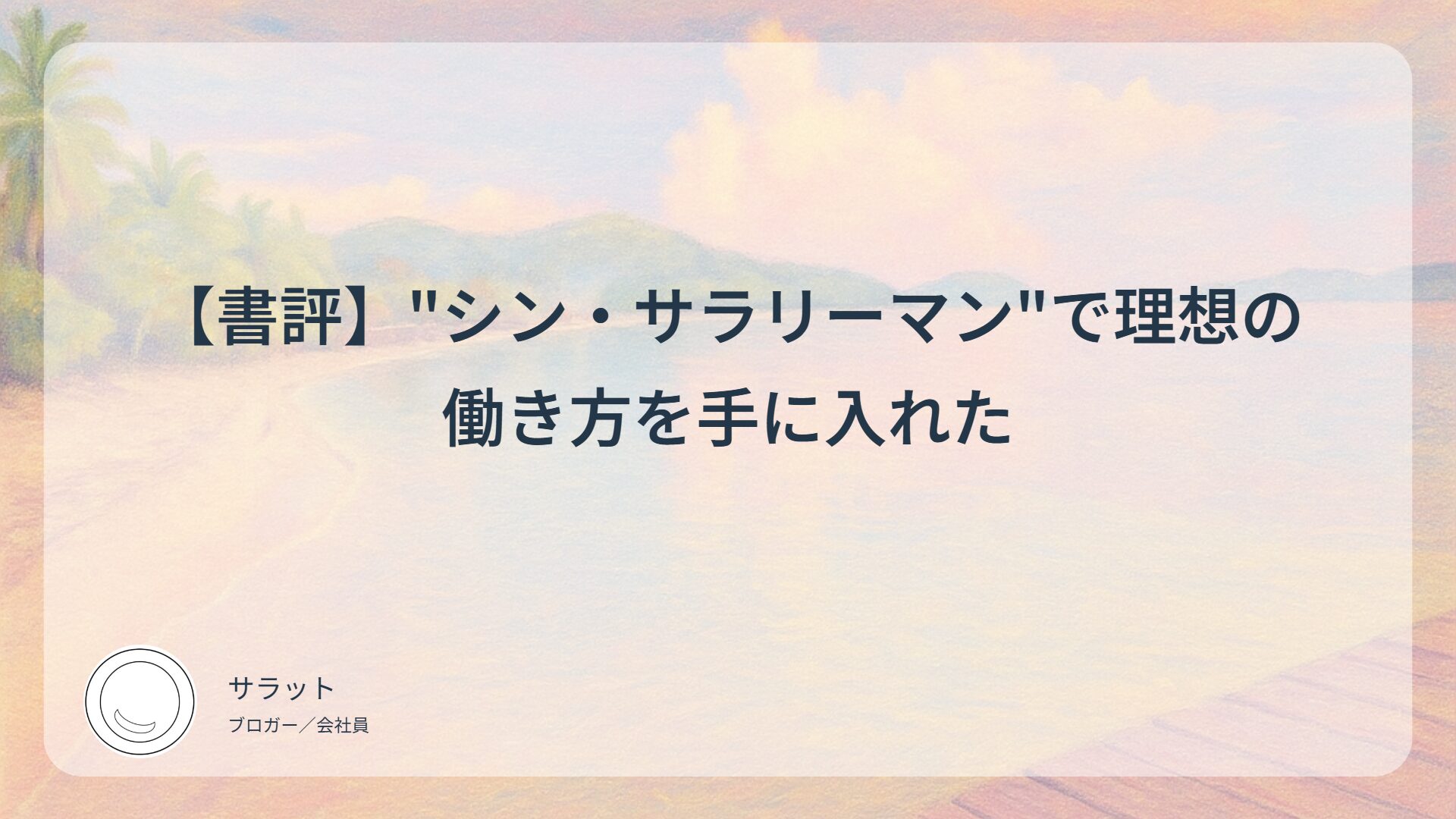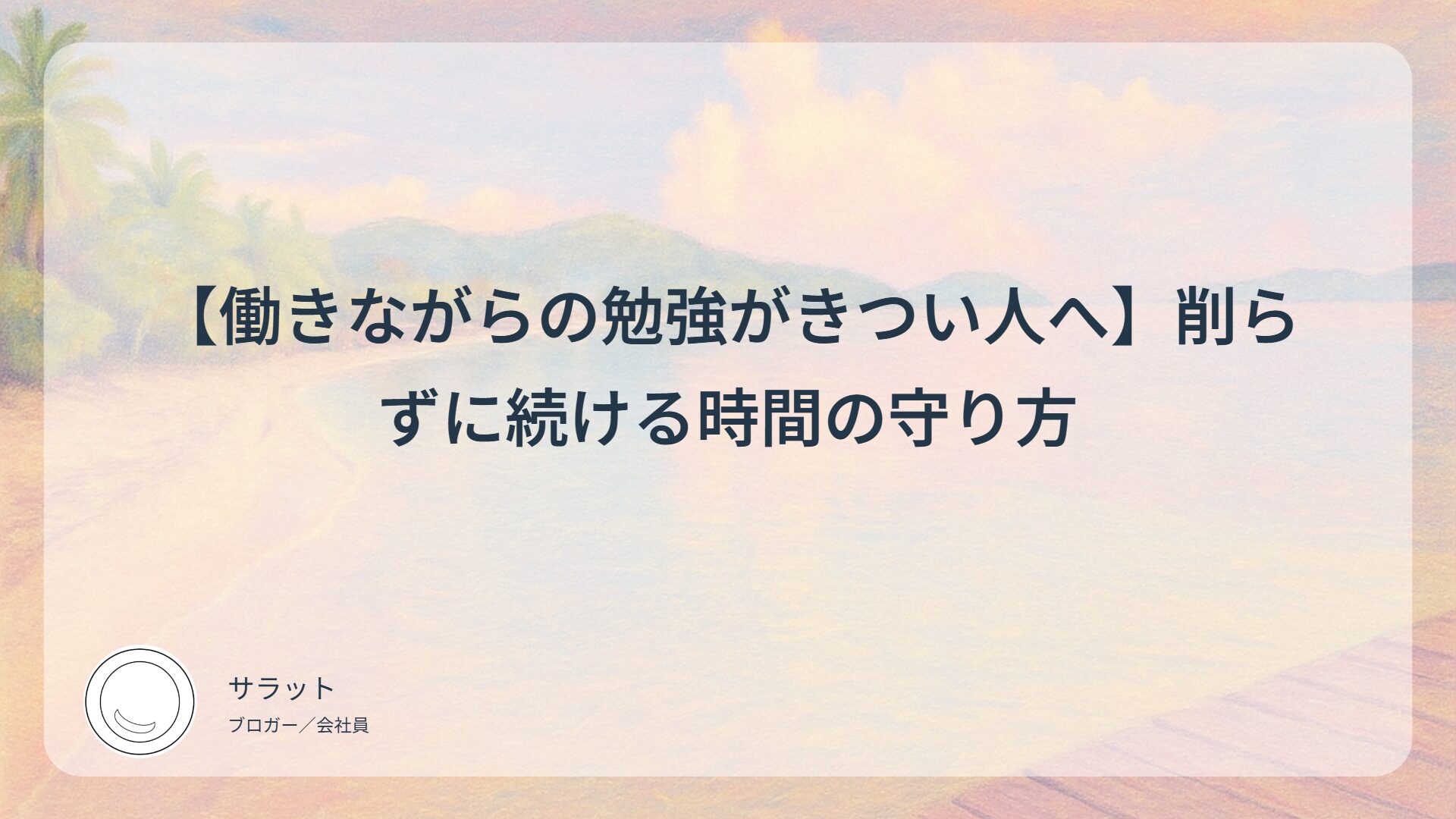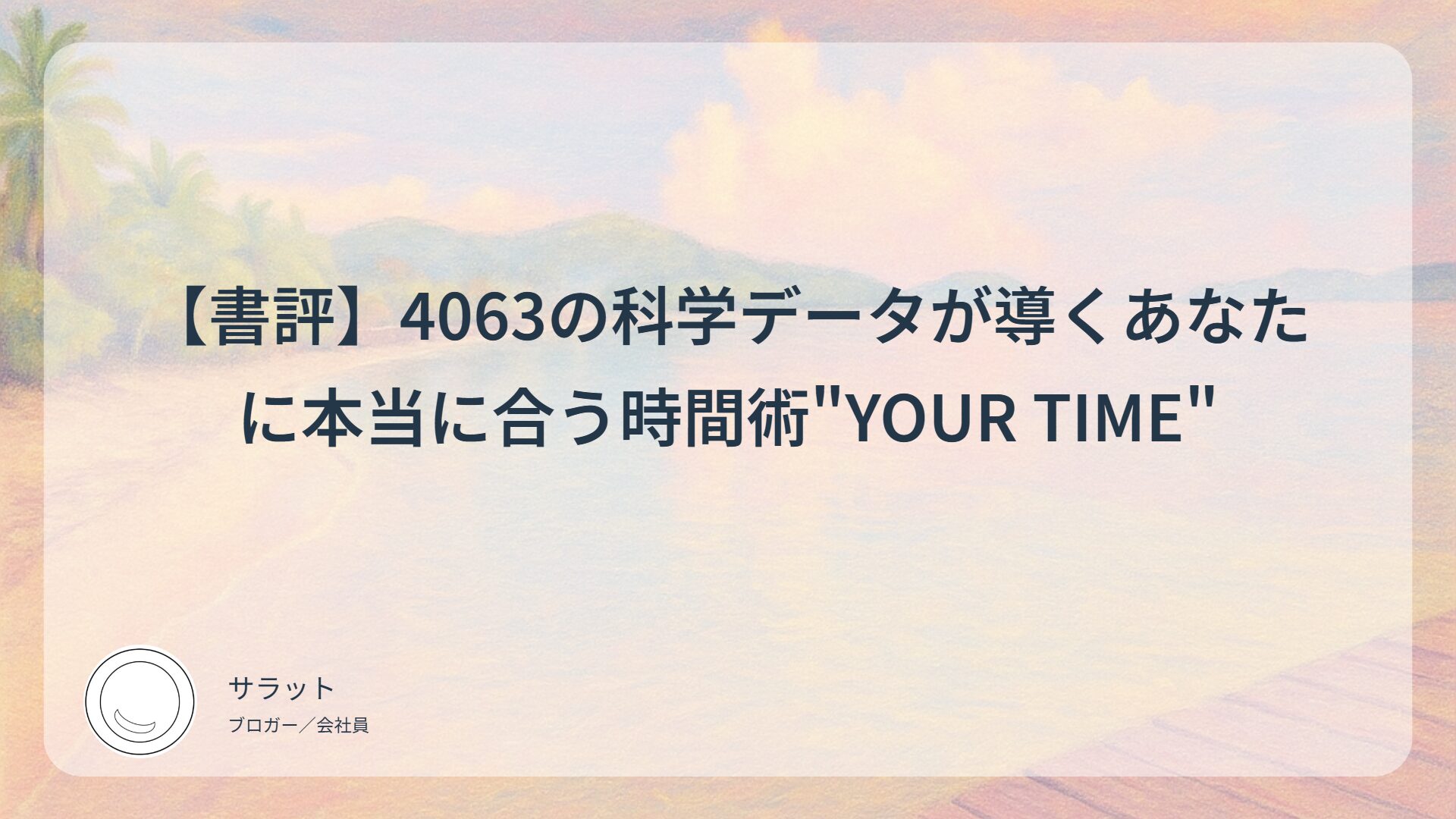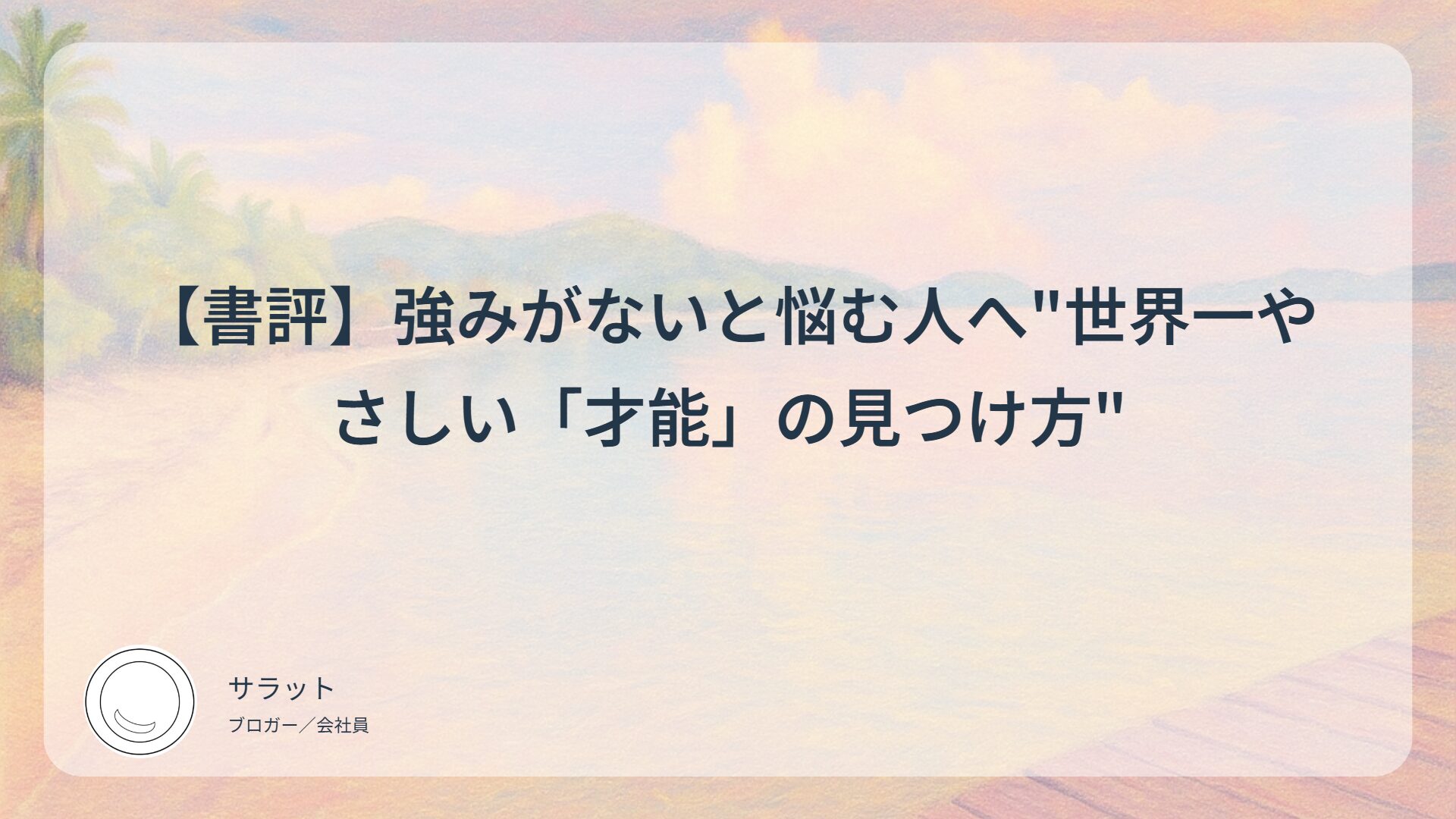【書評】もう迷わない!転職活動の最初の教科書”マンガ 転職の思考法”
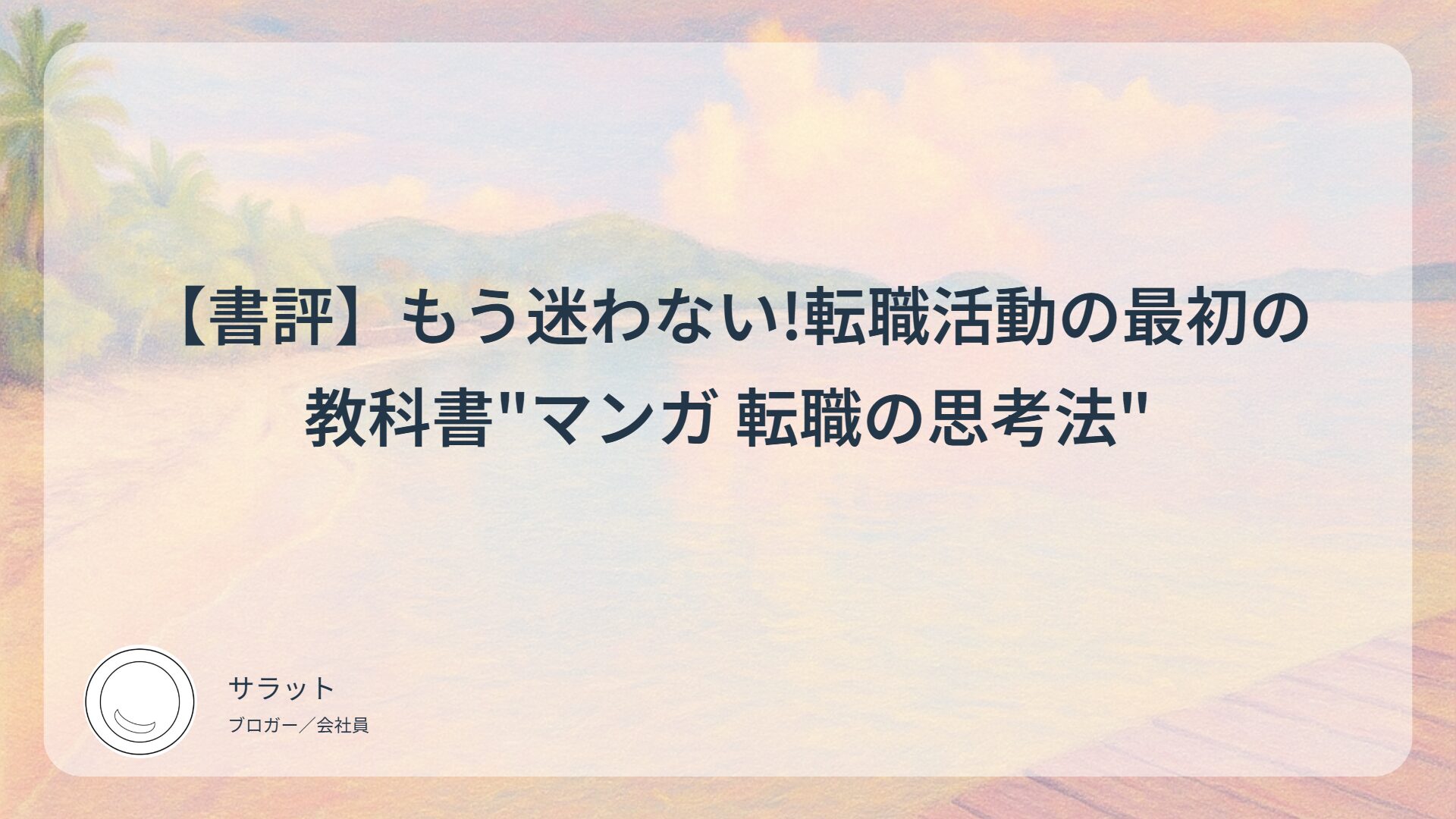
このまま今の会社にいていいのかな…?
でも、いざ転職するにも何から考えればいいかわからない…
あなたは今、そんな漠然としたキャリアへの不安を抱えていませんか?

私も新卒から9年間勤めた会社を辞める前、子どもの誕生も相まって同じような悩みを持っていました。
そんな時に出会ったのが、今回紹介する『マンガ このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法』です。
本書を読んで、転職は”悪”ではなく、人生を豊かにするための”手段”であると気づき、自分の市場価値を客観的に見つめ直すことができました。
本記事では、転職を考え始めたあなたの不安を解消する『転職の思考法』のポイントを、私の実体験を交えながら解説します。

もし内容が気になりましたら、ぜひ本書を手に取ってみてください。
この記事をかいた人(サラット)
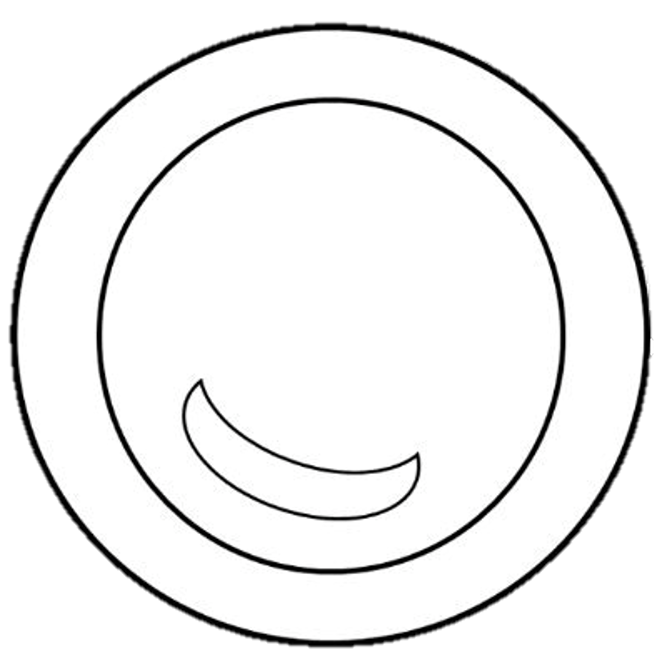
- 都内在住の二児(長男3歳・次男0歳)の父
- 教育業界にて会社員歴12年目
- 育休を2回取得(1回目:1か月、2回目:6か月)
- 営業職→企画職へ転職&フルリモート勤務を実現
- 年間の読書量は50冊以上
- 詳しいプロフィールは”コチラ”
今回紹介する本:「マンガ 転職の思考法」
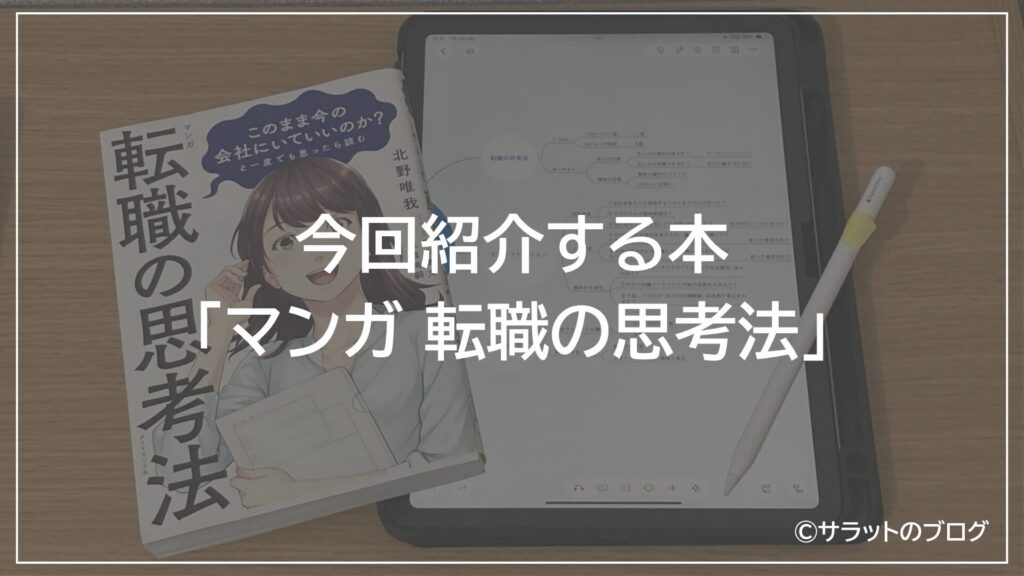
『マンガ このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法』
本書は、20万部を超えるベストセラー『転職の思考法』を、ストーリーを書き下ろしてマンガ化したものです。
物語の主人公は、入社8年目の30歳を目前にした総務部の女性。
マンガを軸にストーリーが進み、要所で活字による詳しい解説が入る構成になっています。

漫画なので、活字が苦手な方でも非常に読みやすく、内容がスッと頭に入ってくる印象です。
| 書名 | マンガ このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法 |
| 著者 | 北野唯我 |
| 出版社 | ダイヤモンド社 |
| 発売日 | 2021年7月 |
| 貢数 | 176貢 |
- 北野唯我さんってどんな人?
-
博報堂、ボストンコンサルティンググループなどを経て、株式会社ワンキャリアの取締役を務めています。
TV番組や新聞などで「職業人生の設計」「組織戦略」の専門家としてコメントすることも多数。ベストセラー『天才を殺す凡人』の著者としても有名です。
広告、戦略コンサル、そして人材(HR)と、キャリアにおける重要かつ多様な業界で実績を積んでこられた「キャリアのプロフェッショナル」です。
数多くの個人と組織を見てきた方だからこそ語れる「転職の思考法」。その知見が惜しみなく本書に詰め込まれています。
「マンガ 転職の思考法」から得られる5つの学び
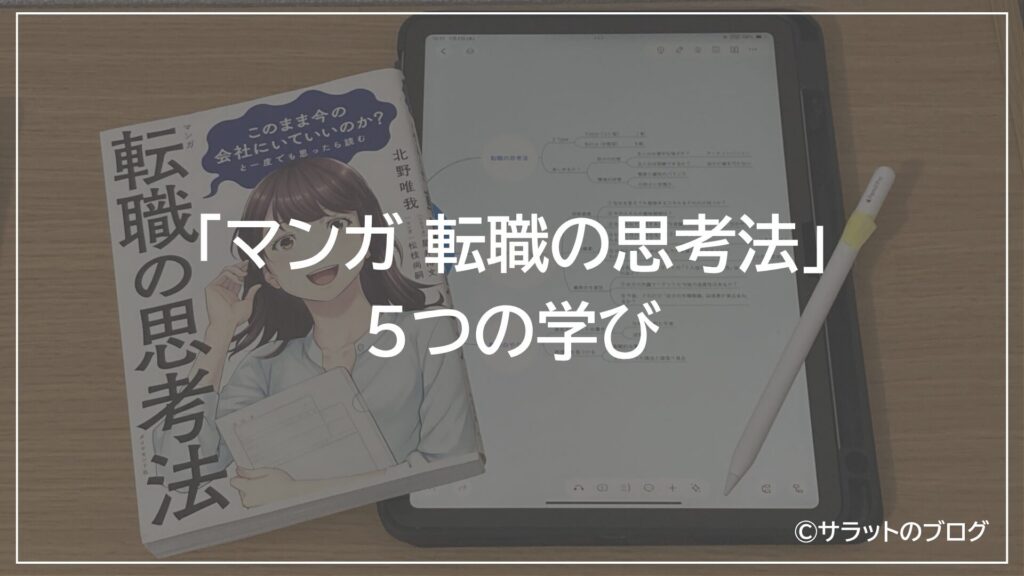
ここからは、本書を読んで「特にここは刺さった」「この考え方には救われた」と感じた5つの学びを私の体験談も交えて解説します。

私にとって面白いのは、「転職する前」と「転職した後」で、響くポイントが全く異なるということ。
転職前は「どうすればいいか」というノウハウに注目していましたが、
転職を経験した今読み返すと、自分の選択が正しかったかを確認する「答え合わせ」のように感じられます。
今回は、そんな両方の視点から、特に重要だと感じた学びを5つに絞ってご紹介します。
「転職は悪ではない」と心から思えた
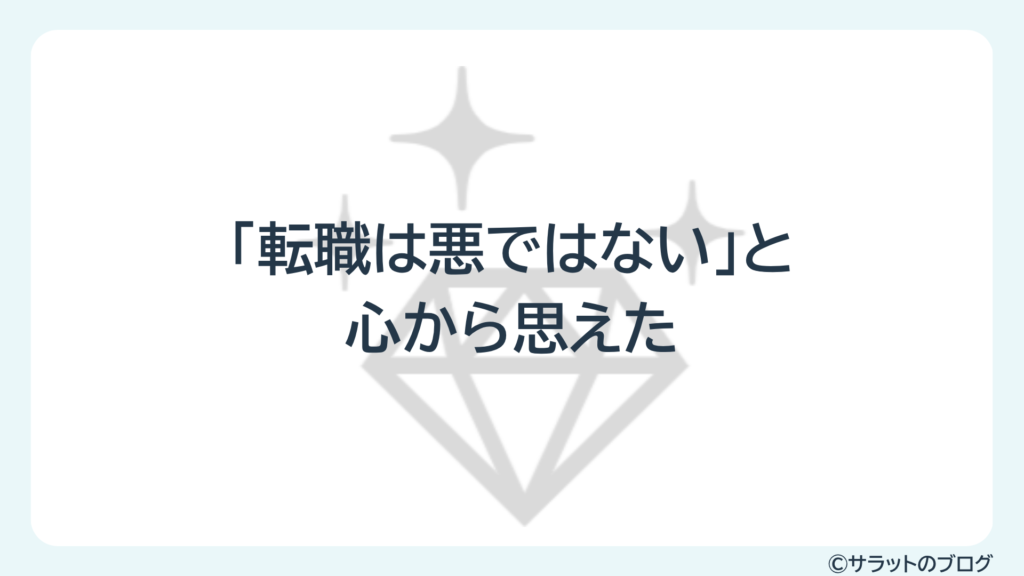
新卒で入社してから9年。
愛着ある会社からの転職を考えたとき、私はどこか「裏切りのような後ろめたさ」を感じていました。

あなたも、もし長く同じ会社に勤めているとしたら、似たような気持ちを抱くかもしれません。
そんな私の心を軽くしてくれたのが、本書にある「転職は悪ではない」という原則です。
終身雇用制度が崩れ、ビジネスが多様化している今、「働く場所を変えてみたい」と思ったなら、会社の外の世界を目指すしかありません。自分の活躍できる場所に行くために、転職という手段を使うのです。
かつての終身雇用が当たり前だった時代と今とでは、前提が大きく異なります。
本書では、現代において「転職」とは、人生の目的を叶えるための有効な”手段”であると断言。

決してネガティブな逃げではなく、自分をより活かせる場所へ移るためのポジティブな選択だ!と。
この言葉のおかげで、私は罪悪感から解放され、「自分の人生のために、最善の選択をしよう」と前向きに覚悟を決めることができました。
自分の市場価値を意識するきっかけになった
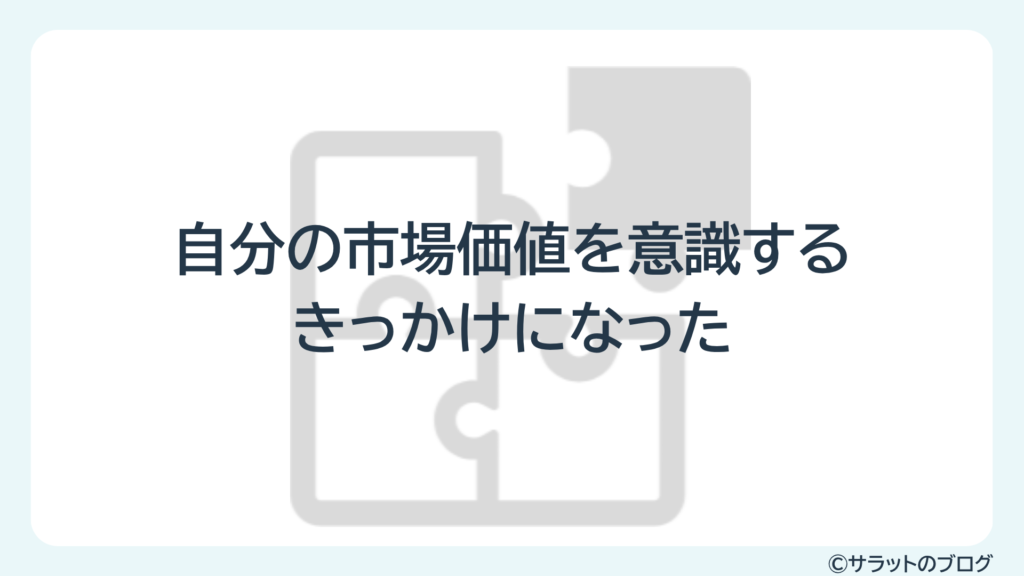
「あなたの市場価値は?」と聞かれて、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。
本書では「自分の市場価値(マーケットバリュー)は3つの要素の掛け算で決まる」と解説されています。
- 技術資産:専門性やスキルなど、他の会社でも通用する技術
- 人的資産:社内外に持つ人脈・ネットワーク
- 業界の生産性:自分がいる業界が、伸びているかどうか

前の2つは何となくイメージできても、ハッとしたのが3つ目の「業界の生産性」。
当時の私は、個人のスキルアップには必死に取り組んでいました。
しかし、所属していた業界は市場全体が縮小しており、どれだけ頑張っても大きな成果に繋がらない…という現実を何度も経験。
個人の努力ではどうにもならない「環境」という要素がある。
そして、「どこで戦うか」を選ぶことは、「どう戦うか」を考えるのと同じくらい重要なのだと、この本は教えてくれました。
自分の努力を正しく成果に繋げるためにも、市場価値という客観的な視点を持つことは非常に重要だと考えさせられます。

市場価値を考えるにあたっては、自身の「強み」を意識することもポイント。下記の記事も興味があればどうぞ!
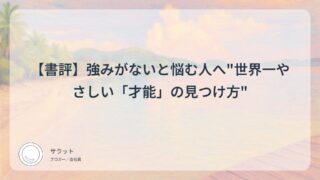
転職エージェントとの上手な付き合い方がわかった
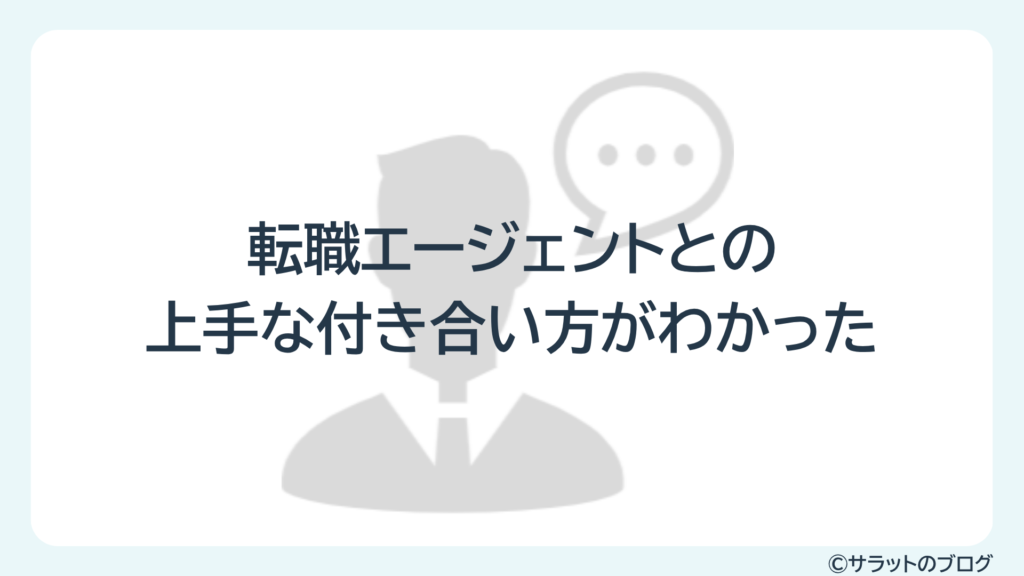
転職活動を始めると、多くの人が「転職エージェント」に登録すると思います。

私も、最終的に2社のエージェントを活用して転職を成功させました。
エージェントは無料で手厚いサポートをしてくれる非常にありがたい存在。
しかし、本書は「エージェントのビジネスモデルを理解した上で、主体的に付き合うことが重要だ」と説きます。
なぜなら、エージェントは、紹介した人材の転職が成立することで、企業から報酬を得ているから。
この仕組みを理解しておくだけで、彼らの提案を客観的に見れるようになり、「良いエージェント」を見極める目も養われます。
ちなみに本書では、良いエージェントを見極める具体的な五箇条も紹介されています。
一例を挙げると下記のような感じ。
面接時どこかよかっただけでなく、入社するうえでの「懸念点」はどこかもフィードバックしてくれる。
私も実際にエージェントと接する上で非常に役立ちました。
彼らを単なる「無料の相談相手」と捉えるのではなく、自分の目的を達成するための「ビジネスパートナー」として捉える。

この視点を持つだけで、転職活動の主導権を自分が握れるようになります。
入社すべき会社を見極める3つの基準を知れた
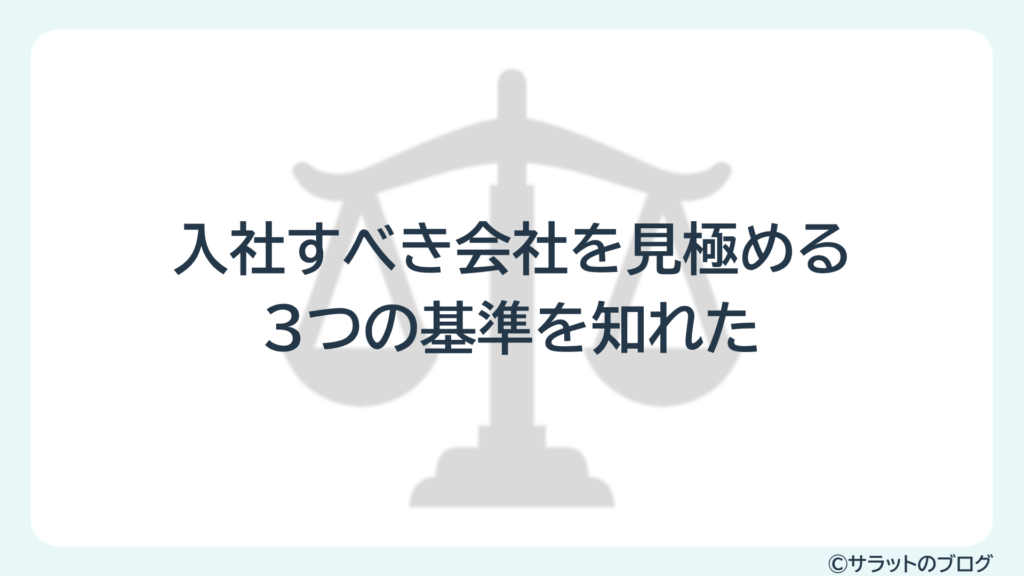
当たり前ですが、内定はゴールではありません。

入社後に「この会社を選んでよかった」と思えることが重要ですよね。
そのミスマッチを防ぐために、本書では会社選びの基準として3つのポイントを挙げています。
- 市場価値(マーケットバリュー)を高められるか
- 自分にとって働きやすい職場であるか
- 活躍できる可能性を秘めているか
特に重要だと感じたのが、3つ目の「活躍できる可能性」をどう見極めるか、という視点です。

活躍できる可能性が低いと、市場価値も高まらないし、働きやすくもないであろうと考えました。
そこで私は、本書の教えを参考に、内定をいただいた後、面接官とは別人の「現場で働く社員さん」と話す機会をセッティングしてもらいました。
聞きたいことは沢山ありましたが、絶対に確認しようと思ったのは下記事項。
現場の方の言葉からは、求人票や面接だけでは決してわからない、たくさんの情報を得ることができました。

この”答え合わせ”の作業が、最終的に入社を決断する上で、何よりも重要な情報になったと確信しています。
本当の安定は「いつでも転職できる」という選択肢から生まれる
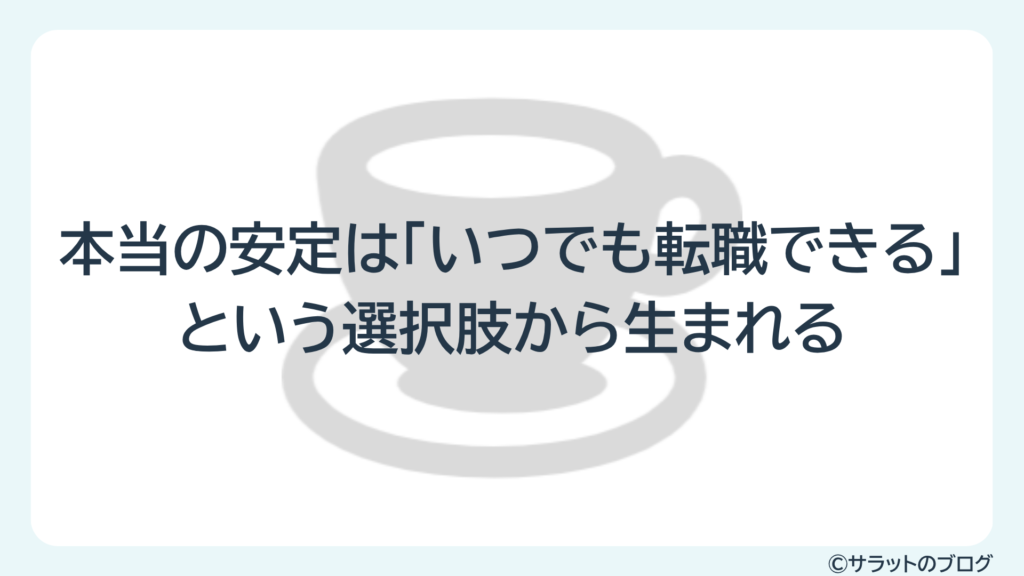
「転職の思考法」の答えは「転職」ではない。「いつでも転職できる」というカードを持つことなんだ
本書が最終的に伝えたいメッセージは、上記だと私は感じています。
「いざとなれば、自分は他の場所でも戦える」
このカードを持っているだけで、心に圧倒的な余裕が生まれます。
今の仕事に依存しなくなるため、理不尽なことがあれば交渉できますし、より主体的に仕事に取り組むようにもなれるのです。
私もこの考え方に出会ってから、自分の市場価値を保つために、定期的に職務経歴書を更新するようになりました。
これは転職の準備というだけでなく、自分の仕事を振り返り、次は何をすべきかを考えるための貴重な習慣になっています。

実際に転職するかどうかは関係ないと考えています。
この「カード」を懐に入れておくことこそが、将来の不安を解消する、何よりの安定に繋がるのです。
この本がオススメな人
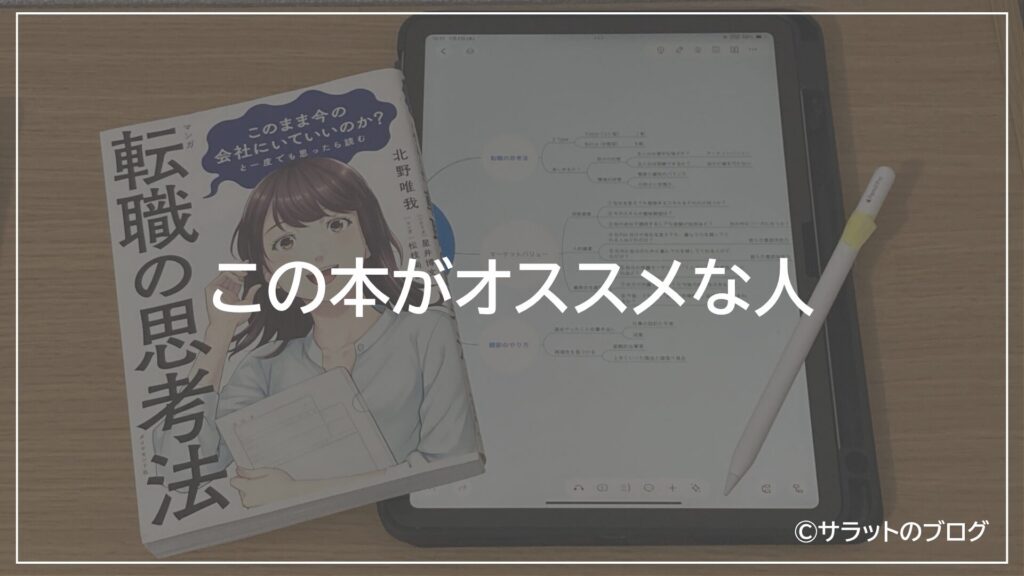
本書は、特に次のような悩みを抱えている人にこそ手に取ってほしい一冊です。
会社を辞めることへの罪悪感や努力が報われない焦り…
そんな袋小路にいる人にとって、「市場価値」という客観的な物差しと、「転職は悪ではない」という覚悟を本書は与えてくれます。
エージェントとの交渉から内定後の最終判断に至るまで、私の転職活動の全行程で”バイブル”として機能してくれた一冊です。

「転職活動の前に読んでよかった!」と心から思えた一冊でした。
この記事のまとめ
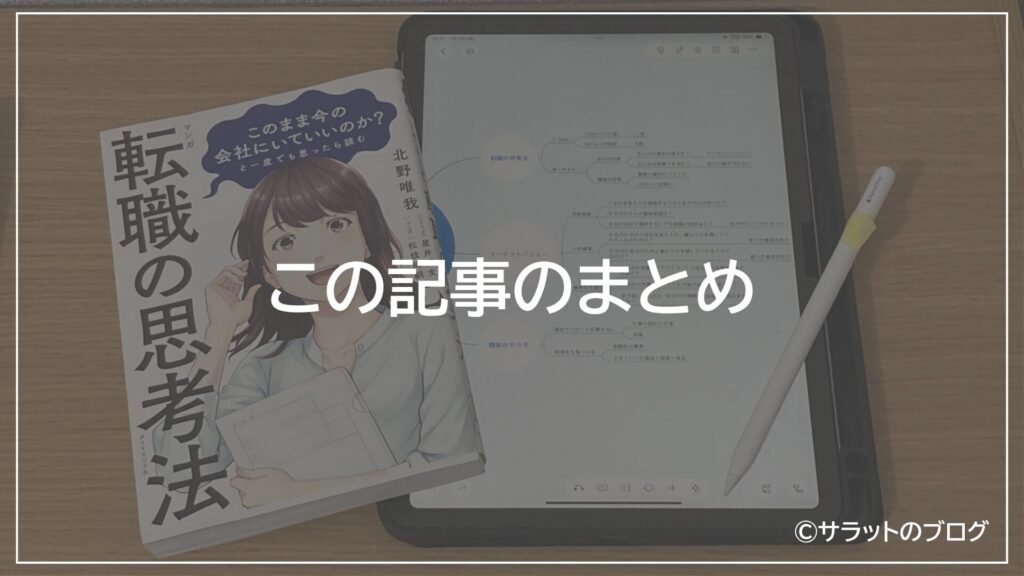
今回は、私のキャリアの転機に大きな影響を与えてくれた一冊、『マンガ 転職の思考法』をご紹介しました。
本書は単なる転職のテクニックを解説した本ではありません。
キャリアへの不安にそっと寄り添い、自分がどうしたいのかを考えるための”指針”を与えてくれる一冊です。
「このまま今の会社にいていいのだろうか…」
もしあなたが、かつての私と同じようにそんな問いを心に抱えているのなら、ぜひ本書を手に取ってみてください。
マンガ仕立てで読みやすく且つ、本質的な学びが満載のこの本が、あなたの「最初の一歩」を力強く後押ししてくれるはずです。

詳細が知りたくなった方は、ぜひ本書を手に取ってみてください。